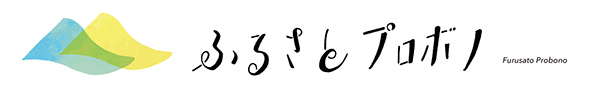緩やかに起伏する丘の連なり、あいまに点在する農業集落の昔懐かしい風情、道の脇にこんもりと連なる槙の木の生垣、そして東に大きくひらける太平洋が、のどかな空気を醸し出す千葉県いすみ市。その名が一躍知れわたる起点となったのは、2017年に成しとげられた「学校給食米の全量有機化」。行政、教育、農業関係者らが一体となり、有機米の生産を広める5年の取り組みの末、実現された体制でした。この成果には、地域外からも高い注目が集まり、各地で各々有機農業に力を注いできた農業者たちからも、称賛の声が上がっています。
学校給食有機化の、その先に見出した課題
一方、当のいすみで徐々に聞こえるようになったのは、必ずしも手放しに喜ぶばかりではない、地元ゆえの多様な声でした。
「学校給食の有機米は、一般には出回っていないんです。だから、消費者の人たちは『私たちはどこへ行けば買えるのですか』、『オーガニックの食材はネット通販で買うもの、ということなら、せっかく産地に住んでいる意味がないね』と。片や生産者の人たちは、『給食にお米を提供するだけでは経営が成り立たない。販路はどうしていけばよいのか』、『給食に有機野菜の提供を始めたけれど、規格がすごく厳しい。規格外の野菜はどうすればよいのだろう』と」
こう実情を明かすのは、NPO法人 いすみライフスタイル研究所(以下、いラ研)理事で、いすみ市の環境保全、学校給食米の有機化に深く関わってきた手塚幸夫さん。
「孫に安全な米を食べさせたい」という高齢の生産者たちの思いにも支えられ、着実に歩を進めてきたいすみの有機農業ですが、いラ研のコアメンバーが共有したのは、その流れの最後に出口、受け皿がないという課題でした。そこで、その出口の滞りを解消すべく、地元の人々が歩いて買いに行けるオーガニック商店、「いすみや」の開店を決断します。さらに、今秋より「ふるさとプロボノ in 農山漁村」に参加したのは、商店づくりとあわせて情報発信を模索するにあたり、外からの目線を持つプロボノワーカーとの協働に意義を見出したからでした。
いラ研理事長・高原和江(写真)さんはいいます。
「いすみやは、衰退していく地元商店街と、地元農業の融合の拠点です。ただ、私たちは商売のプロではありません。このオーガニック運動の『価値を伝えながら』、という点を大事にしていきたいのです」

食・農・環境が交わり合う「いすみオーガニック」
10月初旬、プロボノチームといラ研との協働は、初のオンラインミーティングをもって始動しました。この席で重点をおいて伝えられたのは、いすみ市における学校給食米の有機化が、安全な食べものづくりという「モノ」視点の活動ではなく、千葉県、いすみ市が10数年前から取り組んできた「生物多様性」視点の活動であること。房総半島から失われつつある豊かな里山環境の保全と、その環境への負荷を極力軽減した有機稲作、ひいては市民の食が、分かちがたく結びついた活動であるということでした。
理事の手塚さんは、いラ研の掲げる「いすみオーガニック」のコンセプトと、近年、メディアでも何かと話題のSDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)との本質的な関わりについても言及します。
「SDGsは、“貧困をなくそう”、“飢餓をゼロに”といった17の目標を掲げています。その文言も、ビジュアルも非常にシンプルで、誰もが『私はこれをやります』と取り組める点が優れている。ただ、SDGsの本質は、その17の目標より先に書かれた前文にこそあると、私は思うんです。そこには“誰一人取り残さない”、“経済・社会及び環境の三側面を調和させる”、“平和なくしては持続可能な開発はあり得ず、持続可能な開発なくして平和もあり得ない”とうたわれている。私は、学校給食米を起点に取り組んできたいすみの生物多様性戦略の土台には、この三つの精神のうち、最初の二つが確かにあると考えています」
食・農・環境が交わり合うこと。その調和の価値を大人たちの生活のレイヤーにとどめず、学校給食を通じて教育のレイヤーへ、未来の子どもたちへと受けわたしていくこと。いラ研は今、この活動を「いすみオーガニック」と総称し、「いすみや」を拠点に育んでいこうとしています。その意義をいかにして地域内外へ発信し、巻き込む力を生み出していくか。プロボノチームに期待されているのは、その議論への新たな視点、発想の投げかけです。

俯瞰の視点から見出される価値とは
ミーティングの最後、共に制作していくパンフレットに関していラ研が示した展望は、「伝えたいのは、農家さんをはじめ関わる人々の姿」であり、「生物多様性のような壮大な背景は、後ろに引っ込めておいてもよい」というもの。ここから、プロボノワーカーによる咀嚼と試行錯誤が始まるわけですが、理事長の高原さんは、その道のりにこそ期待を寄せます。
「地域の環境と農業は一体である、という世界観は、ここで生きる人たちにとって、ある意味で当たり前すぎるものだったりもするんです。そこに、プロボノの皆さんが俯瞰の視点でどんな価値を見出し、地域の人たちから何を聞き取っていくのか。大事なのは、パンフレットという最終形ではなく、一つずつ丁寧に積み重ねていく過程だと、私たちは思っています」